この実存主義を代表する哲学者が、フランスのジャン=ポール・サルトルという人物。
彼はなんと、こんなふうに言っています。
「人間は自由の刑に処されている」
……なんだか矛盾しているような言葉ですよね?
「自由」って、普通はポジティブで、うれしいことのはず。
でもなぜ“刑”だなんて、まるで罰のように言うのでしょうか?
では、サルトルっていったいどんな人だったのでしょう?
彼の思想は、今を生きる私たちに、どんなヒントをくれるのでしょうか?
このブログで解説する内容
- サルトルってどんな人
- 実存主義とは?
- サルトルの有名な言葉
- 代表作
- サルトル哲学を現代に当てはめたら?
- まとめ
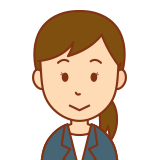
「人間は自由の刑に処されている」ってどういうことかしら。
1. サルトルってどんな人?
彼は20世紀のヨーロッパで、もっとも有名で影響力のある思想家のひとりでした。
サルトルが生まれたのは、第一次世界大戦の前夜。
科学が進歩し、同時に人間の生き方や価値観が大きく揺れ動いていた時代です。
そして、彼の人生は二度の世界大戦を経験することになります。
父親は早くに亡くなり、母親と祖父に育てられたサルトル。
子どもの頃から本が大好きで、図書館にこもっては哲学書を読みふける少年でした。
周囲の子たちが遊んでいる間も、彼は「なぜ世界は存在するのか?」と真剣に考えていたそうです。
成長したサルトルは名門の高等師範学校に進学。
そこで出会ったのが、同じ哲学を学ぶシモーヌ・ド・ボーヴォワールという女性です。
彼女は生涯の恋人であり、思想の同志でもありました。
ふたりは結婚という形を取らず、「自由な愛」と「対等な関係」を貫いたことで知られています。
戦後のヨーロッパでは、サルトルはまさに「知的スター」のような存在でした。
彼の講義やインタビューには多くの若者が押しかけ、新聞・雑誌にも頻繁に登場。
哲学者でありながら、社会運動や政治にも積極的に関わる姿勢が注目されました。
1964年にはノーベル文学賞の受賞が決まりますが、サルトルはなんとこれを辞退します。
「どんな権威からも縛られたくない」という彼の信念が、その決断の理由でした。
このエピソードは、彼の“自由を生きた哲学者”というイメージをさらに強めました。
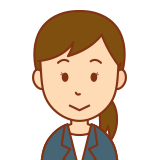
ノーベル賞を断るなんてもったいない!
🗣️ 2. サルトルの有名な言葉
サルトルは、ちょっとドキッとするような印象的な言葉をいくつも残しています。
その中でも、特に有名なのがこのふたつ。
🪐「人間は自由の刑に処されている」
「自由」って、ふつうは嬉しいことですよね。
でもサルトルは、それを“刑”だと言いました。
これは、人間には「何をするか・どう生きるか」を自分で選ぶ自由がある、という意味です。
でもそのぶん、誰のせいにもできず、自分で責任を取らなければならない。それが大変で、時にはつらいこともある…。
そう考えると、「自由であること」は気楽なことではなく、背負うべき運命のようなもの。
それゆえに「刑に処されている」と表現したのです。
🧭「実存は本質に先立つ」
こちらもサルトルを象徴する言葉です。
ちょっと難しそうに見えますが、簡単に言えば
「人は、生まれたあとに“自分が何者か”を選びながら生きていく」という考えです。
「◯◯家の長男だから〜しなきゃ」「女の子なんだから〜すべき」
そういった“決まった役割”を最初から与えられるのではなく、
自分で考えて、自分で選んで、自分をつくっていく。
これが「実存主義」という考え方の核になっています。
サルトルの言葉は、一見むずかしそうですが、
私たちが日々感じる「生きづらさ」や「選択の不安」と深くつながっています。
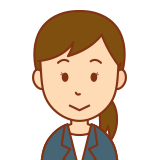
自由には大きな責任がついてくるのね。
📚 4. サルトルの代表作
サルトルは哲学者でありながら、小説や戯曲なども数多く執筆しました。
ここでは、彼の代表作の中から特に有名で読みやすい3作品をご紹介します。
🪞① 嘔吐(おうと) / La Nausée(1938年)
サルトルの代表的な小説作品。
ある男性が日常生活のなかで、世界や自分の存在に“違和感”を抱くようになるという物語です。
おすすめポイント:
・実存主義の核心を小説形式で体験できる
・独特の不安感や世界のズレを、文学的に味わえる
哲学書よりも読みやすく、「サルトルって何を感じてたの?」を体感できる入門作品です。
🎭② 閉ざされた部屋 / Huis Clos(1944年)
3人の男女が死後に送られた“閉ざされた部屋”で、互いを見つめ合い、葛藤する戯曲。
有名なセリフ、
「地獄とは他人のことだ」
はこの作品から生まれました。
おすすめポイント:
・サルトルの対人関係への考え方がわかる
・短くて読みやすく、演劇にもなっている
人間関係のストレスって何?を考えたいときにピッタリの一冊です。
🧠③ 存在と無 / L’Être et le Néant(1943年)
こちらはサルトルの哲学の集大成とも言える大著。
「人間とは何か」「自由とは何か」を本格的に掘り下げています。
おすすめポイント:
・サルトル哲学の本丸に触れたい人向け
・本格的に実存主義を学びたいときに
かなり難解なので、まずは小説や戯曲で雰囲気をつかんでから挑戦するのがオススメです。
どの作品も、“自分とは何か”を深く見つめるきっかけになります。
特に『嘔吐』や『閉ざされた部屋』は、比較的読みやすく実存主義の入口にピッタリ。
ぜひ、気になったものから手にとってみてください。
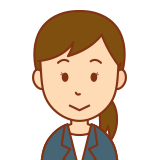
「嘔吐」ってすごいタイトルね気になるわ。
🧭 5. サルトル哲学を現代に当てはめたら?
ジャン=ポール・サルトルが生きたのは、戦争と混乱の時代。
彼の哲学──「実存主義」は、そんな時代に
「人間は自分の生き方を、自分で決めるしかない」というメッセージを投げかけました。
でもこの考え方、実は今の私たちにもグサッと刺さるものがあります。
✅ 就職・進学・SNS──「正解」が見えない現代
今の時代、進路も働き方も恋愛も、生き方は多様化しています。
でもその分、「正解」が見えなくて不安になることもありますよね。
サルトルは言います。
人間は、まず存在し、あとから自分をつくっていく。
つまり、“最初から決まった自分”なんてない。
私たちは、選んで、決めて、失敗して、試行錯誤して、やっと「自分」になっていくんです。
✅ 自由の重さに押しつぶされそうなとき
選択肢が多いのは良いことのようで、
「間違えたらどうしよう」「何を選べばいいかわからない」と悩む人も多いはず。
サルトルはこれを、
人間は自由の刑に処されている
と表現しました。
自由には責任がともなう。
「自分で選ばなきゃいけない」自由は、ある意味で重荷でもあるんですね。
✅ 他人の目が気になるSNS時代に
SNSで「いいね」やフォロワー数が気になる…
誰かの目が気になって、自分を演じてしまう…そんな時代に生きる私たち。
サルトルの有名な言葉に、
地獄とは他人のことだ
というフレーズがあります。
これは「他人の視線に縛られ、自分らしくあれなくなること」の苦しさを表しています。
💡 サルトルがくれるヒント
サルトル哲学のすごいところは、
それが机上の空論じゃなくて、今を生きる私たちにも役立つ“考え方”だという点です。
- 迷ってもいい。人は失敗しながら自分をつくっていく
- 自分で選ぶという「自由」を受け入れる
- 他人ではなく、自分に責任を持つ
こうした視点をもつだけで、
ちょっと生きやすくなる気がしませんか?
📌 6. まとめ──サルトル哲学が教えてくれること
✅ 1. 自由とは「選ぶこと」そして「責任を持つこと」
✅ 2. 「正解がない時代」こそ、実存主義の出番
✅ 3. 他人に振り回されず、「自分」を生きる
🌙 最後に──サルトルという人
サルトルは、人生の最期まで「考えること」をやめませんでした。
ノーベル文学賞の受賞を辞退したのも、体制に迎合せず、自分の哲学に忠実に生きようとした姿勢の表れです。
晩年は視力をほとんど失いながらも、
愛する哲学者ボーヴォワールとともに、静かに、でも深く世の中を見つめていたそうです。
「人間は、自分自身の選択で人生を形づくる」
その厳しさと優しさを教えてくれるサルトルの言葉は、今もなお、私たちの背中をそっと押してくれます。
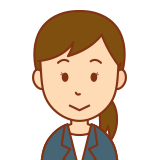
自由とは何なのか考えさせられたわ。
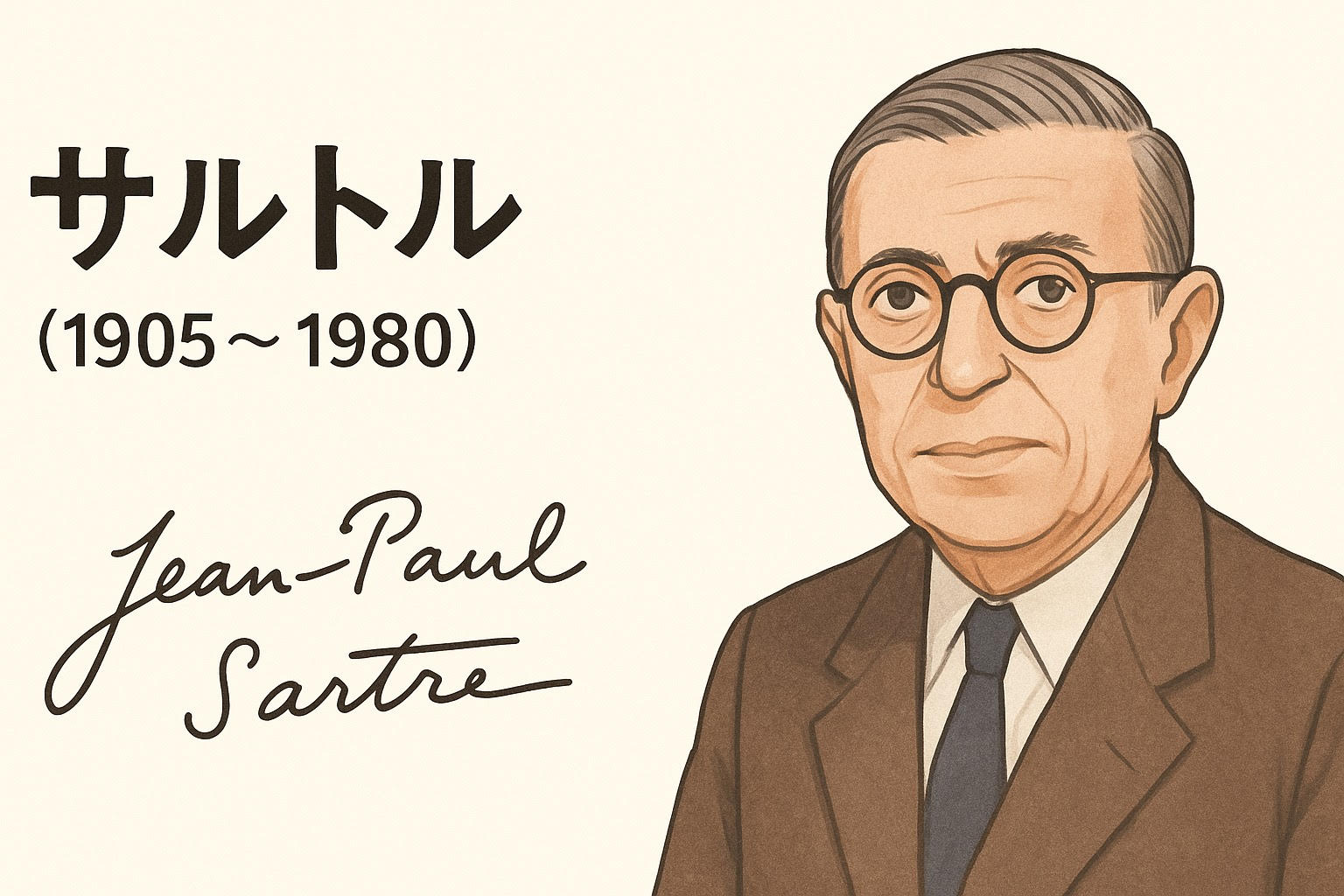
コメント